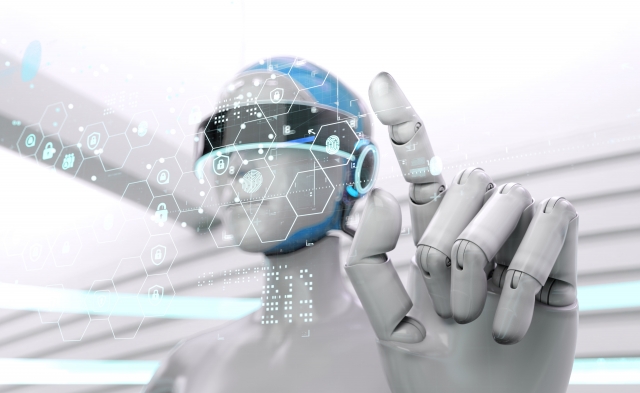アナはハンスにキスを求めたが、その事情を知ったハンスの態度は豹変する。ハンスはアナを愛してなんかいなかった。兄弟の末っ子に生まれたハンスは出世のチャンスなどないと悟っていたため、成り上がるために、君たちに近づいたんだと、喋りまくる。
だが、詰めの甘いハンスは死にそうなアナを部屋に閉じ込めただけにとどめる。ここで息の根を止めておけばよかったものを、あくまでも自然死を望んでしまったハンスは悪になりきれなかった。ここはディズニーだから、というだけではなく物語特有の悪の甘さみたいなものがある。どんな卑劣な悪にも悪になりきらせないところに物語の脹らみはある。悪になりきらせてしまうと、物語のおもしろみが薄れることは多々ある。サスペンスなどで、銃を突きつけられて絶体絶命、というときに、必ず間一髪で救われたりするのは、物語だからである。現実ならあっという間に撃たれてしまう。しかし物語は説明が犯人の告白によってなされたり、まごまごしているあいだに、チャンスがやってくる。
『お前を殺すときが来たようだ、、ふふ、恨むのなら裏切り者を恨むんだな、俺はなにも悪くない。。。』
そうこうしているうちに正義の味方が駆けつけ、バキューンと犯人の銃を落とす…。と、お決まりのシーンがそこかしこの物語には見られる。これは悪人にもどこかに弱点を設けることで心理が複雑になり、物語の展開を助ける枝となる。ディズニー映画は子供だけでなく大人も説得しなければならないから、ハンスの王位に関する動機にしても、子供ではピンと来なさそうな辻褄でもしっかりと入れ、人間の甘さというか弱さのような一面でスパイスを効かせて隙のないものにしている。
側近たちには、アナは死んだ、と頭を抱えながらいい演技を入れて伝える。そしてエルサの処刑へとことを運ぶ。
クリストフは城を後にしながらも、葛藤していた。これでよかったんだ。これは敗者または後悔にまみれた者の台詞だ。しかし持つべきものは友。相棒のトナカイに諭され、城へと戻る。これは家族愛の物語であるのと同時に友情の物語でもある。次のオラフの行為にもそれを見て取ることができる。
オラフは、アナを温めるために自分の体が溶けてしまうのにもかかわらず、暖炉に火を点け、温めようとする。止めようとするアナに、愛とは自分のことよりも相手のことを考えることだ、と伝える。愛というところがからキリスト教的な発想であることが強く伺えるが、宮沢賢治の助けようとしている蛙がサソリに食べられてしまうあの名場面にもあるように、仏教でもあり、この他人を思うことというのは宗教や文化を越えて人類にとって普遍的なものである。しかしオラフは人類ではない。果たしてあなたは人類以外にも愛はあると思うだろうか?私にはわからない。
オラフはメッセンジャーとして、クリストフがアナを愛していることを伝え、彼のキャラクターを全うする。もし別の展開があるとすれば、オラフはここで溶けて死んでしまってもよかったかもしれない。それ以上のメッセージがあるだろうか。でも死ななくても十分に伝わればそれでいいのかもしれない。余計なお涙ちょうだい場面はなくてもいいのだ…。